「あれ、こんなに神経質だったっけ?」
ドアの開け閉め、食器の重なる音、足音…日々の音に、知らぬ間に心が擦り減っていく。
無意識に蓄積される音のストレス。それは、大きな音ではなく“じわじわと忍び寄る”音だったりします。
音に敏感なのは、あなたの感覚が繊細で豊かだからということ。
その感性を守るために、どう生活を組み直せるかを一緒に考えてみませんか?
静けさを求める理由は「耳」ではなく「心」が知っている
誰もいない部屋。静かなはずなのに、壁越しにかすかに聞こえるテレビの声。
それだけで、なぜか全身がざわついて、読んでいた本の内容も頭に入ってこない。
気にならない人には一生わからないだろうな…、と思いながらも、あなたは“気にしている自分”に少し罪悪感さえ覚えてしまう。
でも、音は心のコンディションと密接に関係しています。
無意識に「この音は安全か?不快か?」を判断し続ける脳にとって、生活音は決して無害な存在ではないのです。
“うるさい”の正体は「境界線の侵害」
音に敏感な人は、「自分の空間」と「他者の存在」との境界が曖昧になった瞬間にストレスを感じます。
それは騒音ではなく、“気配”に近いものかもしれません。
壁を超えてくる足音や話し声に対して、「ここは私の空間なのに…」と、心のプライバシーが侵されたような感覚になる。
それが重なれば、「うるさい」の一言では表現しきれない、複雑な不快感へと変わっていきます。
「気にしすぎ」とは違う、音に反応する“感受性”
誰かに「そんなの気にしないで」と言われたとき、あなたの中には小さな反発が芽生えたかもしれません。
「わかってくれない」ではなく、「この感覚は否定できない」という、自分の中の確かなリアリティ。
ある感受性の高い人の話
「うちは木造の集合住宅で、夜になると階上のイスを引く音がゴリゴリ響いてきて…。
眠る直前の“静けさの中”に突然あれが来ると、心臓がきゅっとなって眠れなくなるんです。」
これは極端な話ではなく、多くの人が体験している“静寂とノイズのせめぎ合い”の現実。
音に反応すること自体が「弱さ」ではなく、実は「感受性の高さ」ゆえの反応なのかもしれません。
「どうしようもない音」に、できること
音は“止める”ことが難しいからこそ、「受け取り方」を変えるアプローチが鍵になります。
物理対策:グッズに頼ってみる
- ノイズキャンセルイヤホン:街でも部屋でも“自分の音場”がつくれる
- ホワイトノイズマシン:不規則な生活音をマスキング
- 耳栓:安価で即効性、寝るときだけでも安心
中でも“音をシャットアウトする”より、“音の主導権を握る”という感覚をもたらしてくれるものは、思った以上に心強い味方になります。
環境調整:生活スタイルに余白をつくる
音ストレスにさらされやすいのは、心に余裕がないとき。
あえて無音の時間を設けてみたり、自然音を流してリセットしたり。
「音を減らす」ではなく、「心をゆるめる」視点が、新しい感覚の整理に繋がります。
内面的対策:思考の再解釈
「音がうるさい」→「それだけ私は周囲に敏感なんだ」
「集中できない」→「今は自分にとって無理のある環境なんだな」
そんなふうに、自分を責めるのではなく“理解し直す”言葉が、意外と効いてくることもあります。
音を“敵”にしない、新しい距離感のつくりかた
音は避けられない。けれど、それとどう付き合うかは、自分で選べる余地があります。
・「今日は耳が疲れてるから早めに休もう」
・「この音が気になるということは、他のことにも余裕がないのかも」
・「静かな場所に行って、心のバッテリーを充電しよう」
“聞こえてくる音”よりも、“聞こえてきたときの自分”に目を向ける。
そんな習慣が、あなたの感覚を少しずつ穏やかに整えてくれるはずです。
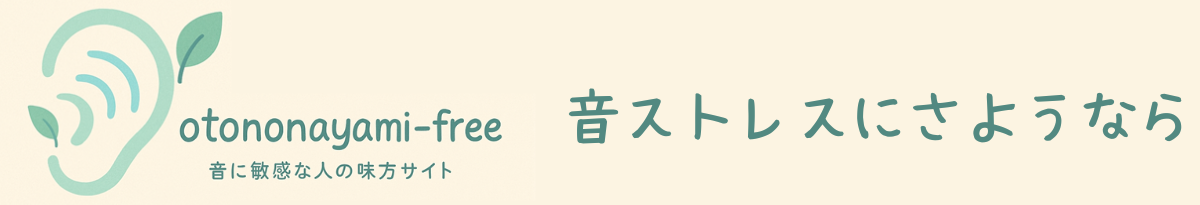

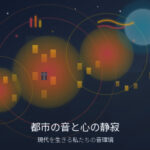
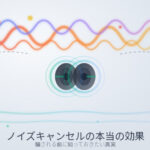
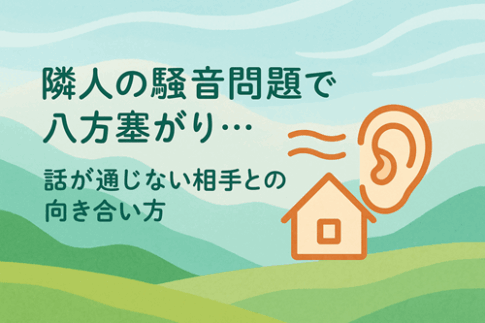
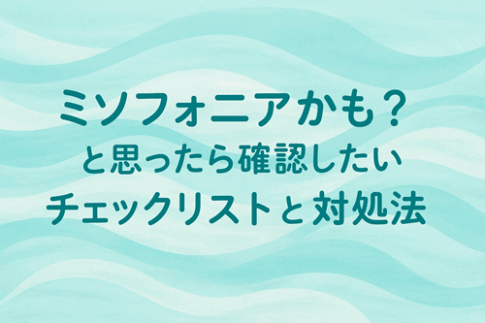
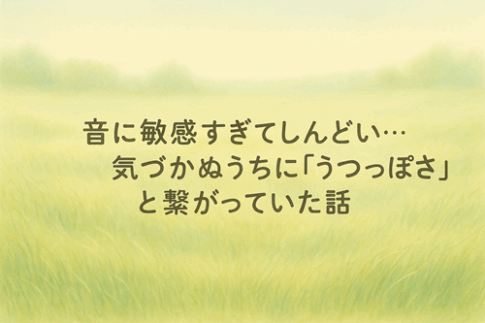
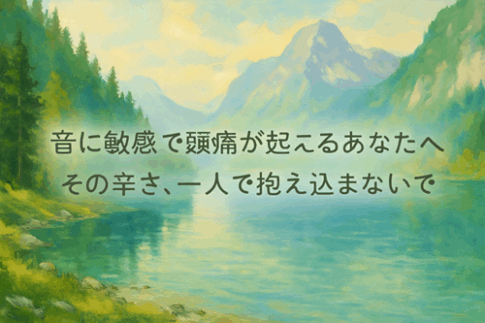
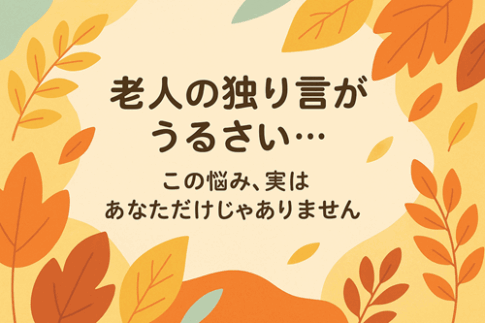
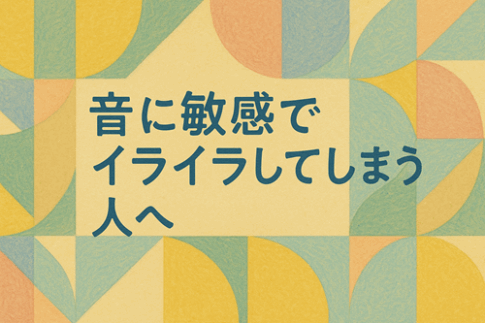


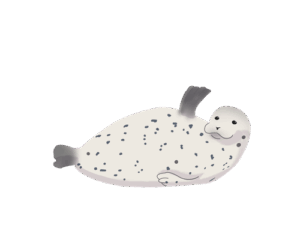
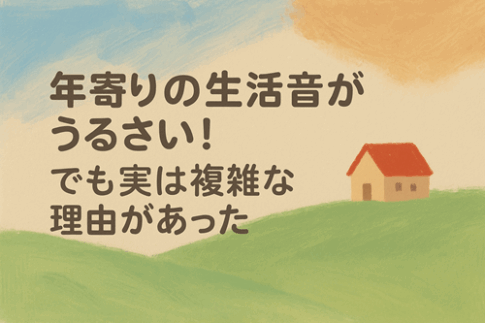
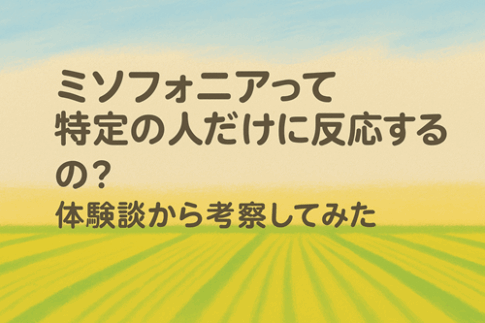
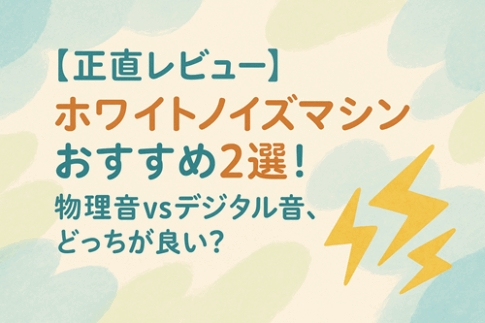

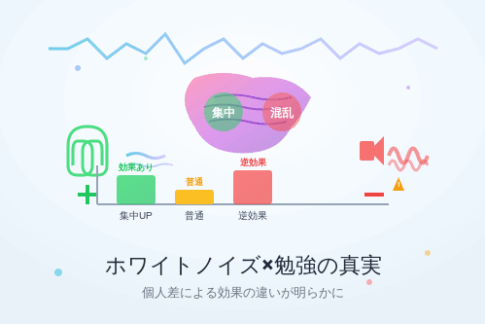

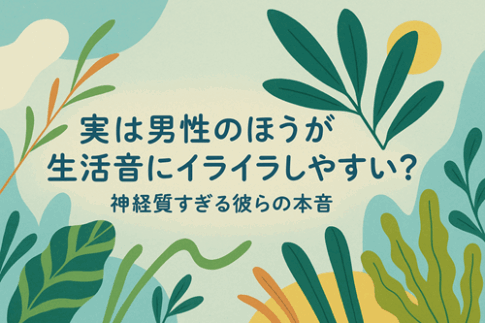
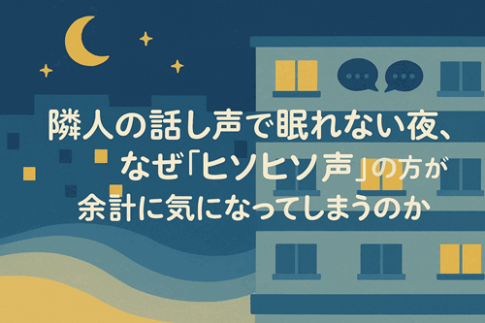
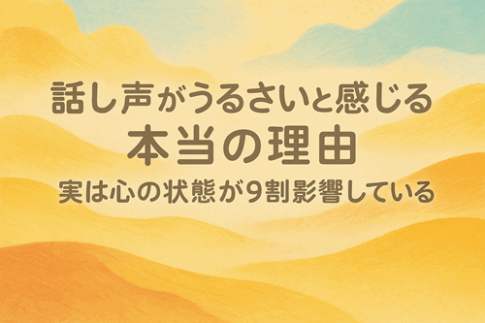
コメントを残す