「また隣の人のタイピング音が気になって集中できない…」「家族の生活音でイライラしてしまう自分が嫌になる」。音に敏感なあなたは、毎日このような小さな戦いを繰り返していませんか?
対処法は必ずあるという気持ちが大切です。あきらめて人を責める前に、まずは自分らしい工夫から始めてみませんか?みんなそれぞれに工夫して暮らしているんですから。
音に敏感な人が直面する日常の困りごと
音に敏感だと、本当に一日中気になる音だらけですよね。朝起きた瞬間から夜寝るまで、あらゆる音が耳に飛び込んできて、心が休まる暇がない。
ドアの開閉音、椅子を引く音、咀嚼音、ペンを回す音、キーボードのタッチ音、鼻をすする音…。一つ一つは些細な音なのに、なぜかとても気になってしまう。
「普通の人はなんで平気なんだろう?」って不思議に思いますよね。
場所別・よくある音の悩み
職場での音ストレス
オープンオフィスって、音に敏感な人には本当に辛い環境です。隣の席の電話の声、キーボードを強く叩く音、貧乏ゆすりの音。集中したいのに音が気になって、仕事の効率が落ちてしまうんですよね。
家庭での音ストレス
家族の生活音が気になってしまって、リラックスできるはずの家なのに心が休まらない。テレビの音量、洗濯機の音、食器を洗う音。愛する家族の音なのに、イライラしてしまう自分に罪悪感を感じたり。
外出先での音ストレス
電車の中のスマホの音、カフェでの大きな笑い声、工事現場の音。逃げ場がない状況でのストレスは、本当に疲れてしまいます。
なぜ音でこんなに困ってしまうの?
脳の情報処理の特性
音に敏感な人の脳は、音の情報をより詳細に、より強く処理してしまう特性があります。つまり、生まれ持った個性の一つなんですよね。
「気にしすぎ」って言われても、脳の仕組みが違うんだから、気にするなと言われても無理な話です。車のエンジン音を「単なる音」として処理する人もいれば、「うるさい雑音」として感じる人もいる。それと同じことなんです。
予測できない音への反応
突然鳴る音や、不規則な音ほどストレスを感じやすいのも、音に敏感な人の特徴です。
エアコンの音みたいに一定のリズムの音は慣れるけれど、ペンをカチカチする音や、椅子をガタガタさせる音は、いつ鳴るか分からないから余計に気になってしまう。
感情との連動
音のストレスは、感情とも密接に関係しています。疲れている時、ストレスを感じている時、体調が悪い時は、普段気にならない音でもイライラしてしまうことがありますよね。
私も含め、みなさん工夫して暮らしていると思う
音に敏感な人って、実はとても工夫上手だと思うんです。私も含め、みなさん工夫して暮らしていると思うんですよね。
イヤホンを常に持ち歩いたり、座る位置を考えたり、時間をずらして行動したり。みんなそれぞれに、自分なりの対策を編み出している。
小さな工夫の積み重ね
「こんな小さなことで…」って思われるかもしれないけれど、音に敏感な人にとっては大切な工夫なんです。
カフェで壁際の席を選ぶ、電車では車両の端に乗る、家では音の出にくいスリッパを使う。一つ一つは小さなことだけれど、積み重ねると大きな効果があります。
対処法は必ずある。あきらめない気持ちが大切
対処法は必ずあるという気持ちが大切だと、私は思っています。
完璧な解決策がすぐに見つからなくても、少しでも楽になる方法は必ずあるはず。あきらめて人を責めたり、自分を責めたりする前に、まずは自分にできることから始めてみませんか?
具体的な対処法のアイデア
物理的な対策
ノイズキャンセリングイヤホン、耳栓、防音グッズなど、音を物理的に遮断する方法。技術の進歩で、昔に比べてかなり効果的な商品が増えています。
環境の工夫
座る位置を変える、時間をずらす、場所を移動するなど、音の発生源から距離を取る工夫。
音で音をマスキング
ホワイトノイズや自然音で、気になる音を聞こえにくくする方法。自分でコントロールできる音で、コントロールできない音を包み込むイメージです。
メンタル面でのケア
リラックス法や呼吸法で、音へのストレス反応を和らげる方法。完璧に音を消すことはできなくても、ストレスの感じ方は変えられます。
自分らしく対処していくために
あきらめて人を責める前に自分らしく対処していきたいと私は思っているんです。
他人を変えることはできないけれど、自分の対処法は工夫できる。音に敏感な自分を否定するのではなく、音に敏感だからこそできる工夫を見つけていく。
対処法を見つけるコツ
小さなことから始める
「完璧な対策を見つけなきゃ」と思わずに、「今日はちょっとだけ楽になった」という小さな成功を積み重ねていく。
いろいろ試してみる
一つの方法がダメでも、他にもたくさんの選択肢があります。自分に合った方法は、試してみないと分からないものです。
無理をしない
「音に敏感な自分を治さなきゃ」と思わないこと。敏感さは個性の一つです。上手に付き合っていければそれで十分。
音に敏感な毎日は大変だけれど、同じような感覚を持つ人はたくさんいます。一人で抱え込まずに、みんなで工夫を共有しながら、少しずつ楽になっていきましょう。
あなたなりの対処法が見つかりますように。音との上手な付き合い方は、きっとあるはずです。
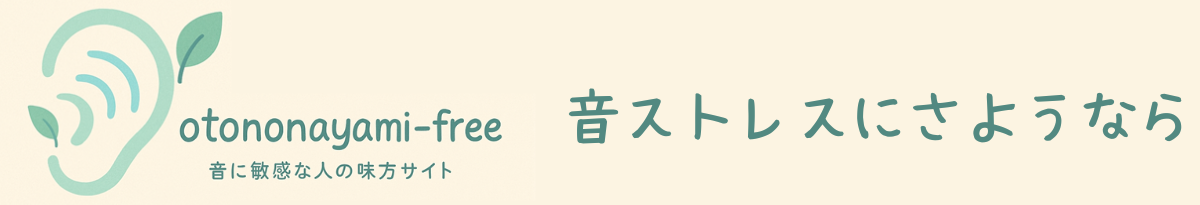
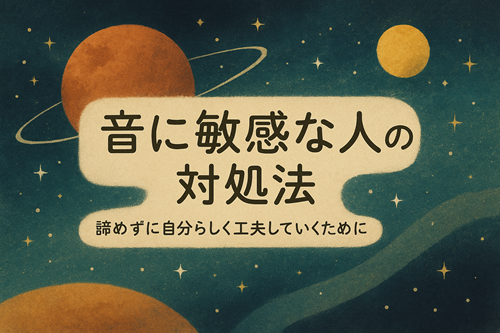
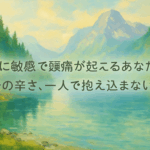
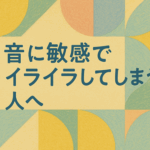
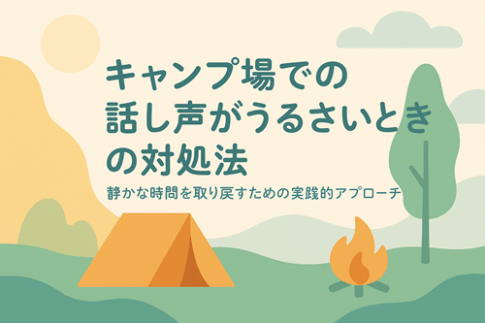
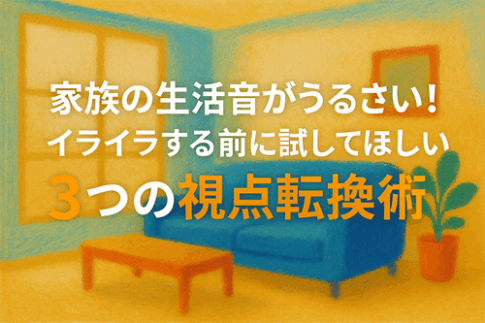
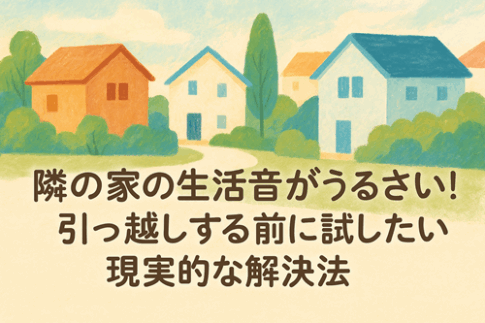

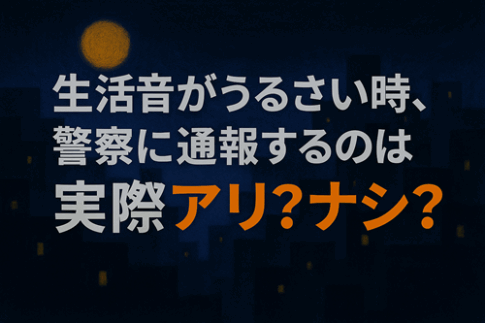
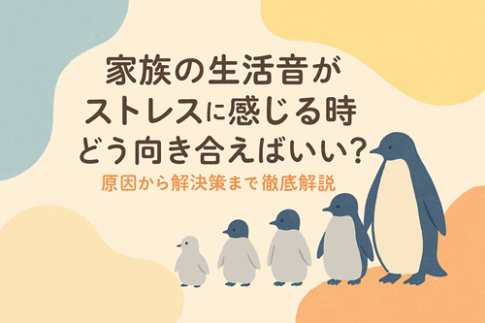


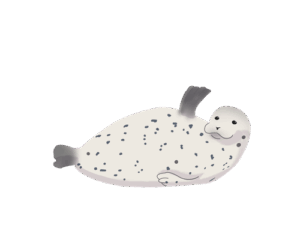
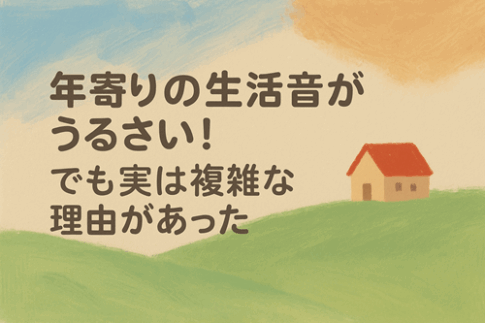
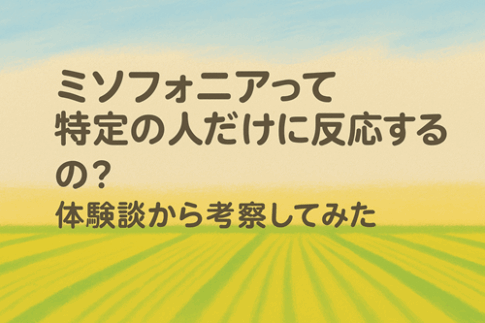
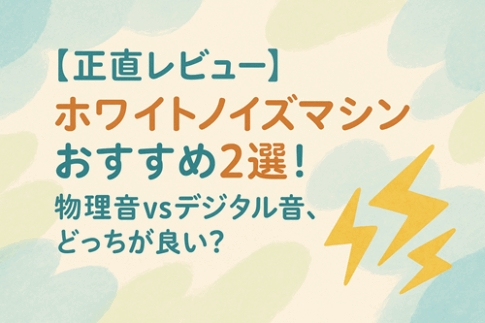

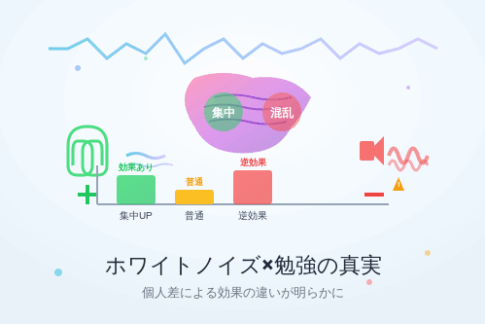
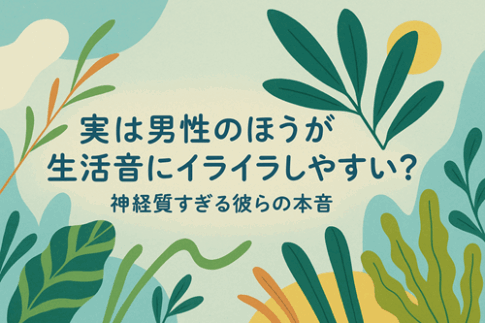
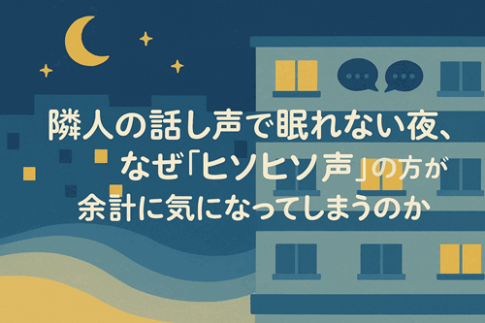
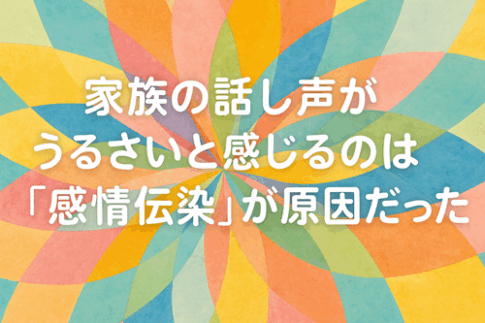
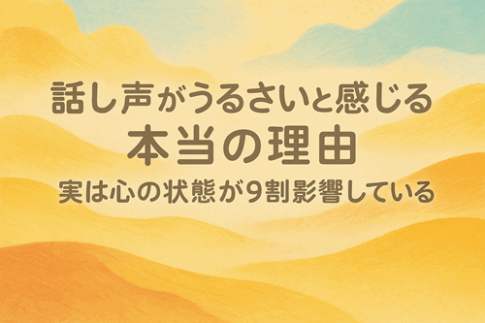
コメントを残す