集合住宅での生活音トラブル、本当に悩ましいですよね。直接言うのは気まずいし、でも我慢し続けるのも限界がある。そんな時の選択肢の一つが「管理会社に注意喚起文書の掲示を依頼する」こと。
実際にやってみた結果、一定の効果はあったものの、予想外の展開も待っていました。この記事では、注意喚起文書の効果と注意点、そして具体的な対処法について、リアルな体験を交えてお話しします。
生活音の注意喚起文書とは?効果的な対処法の一つ
生活音トラブルって、本当に神経をすり減らしますよね。特に朝の時間帯や夜遅くの音は、生活リズムを乱されて心身ともに疲れてしまいます。
注意喚起文書とは、管理会社や大家さんが建物内に掲示する、住民のマナー向上を促す文書のこと。直接的な苦情ではなく、「一般的なお願い」として掲示されるため、角が立ちにくいのが特徴です。
注意喚起文書が有効な生活音トラブル
実際に注意喚起文書で改善が期待できる音のトラブルには、こんなものがあります:
・早朝や深夜の生活音 洗濯機の音、掃除機の音、テレビの音量など、時間帯を考慮してもらえる可能性が高い音です。
・ペットの鳴き声 犬の吠え声や猫の鳴き声は、飼い主が気づいていないケースも多いもの。文書で注意喚起されることで、初めて問題を認識する場合があります。
・楽器の演奏音 ピアノやギターなどの楽器は、演奏者にとっては趣味の時間でも、近隣住民にとっては騒音になることがあります。
でも正直なところ、「これで本当に改善されるのかな?」って半信半疑になる気持ち、すごくよくわかります。
注意喚起文書の一般的な内容と効果
管理会社が作成する注意喚起文書は、大体こんな内容になります:
「住民の皆様へ 生活音についてのお願い」といったタイトルで、早朝・深夜の音に注意してもらう旨が記載されます。特定の部屋や住民を指すのではなく、建物全体への一般的な呼びかけという形を取るのが基本です。
効果については、正直言って「人による」というのが本音。でも、意外と「言われて初めて気づいた」という人も多いんです。
実際の体験談:犬の早朝吠えに悩んで注意喚起文書を依頼した結果
ここで、実際に注意喚起文書を依頼した体験談をお話しします。
問題の発端:毎朝5時から始まる犬の鳴き声
隣室で飼われている犬が、毎朝5時頃から吠え始めるようになりました。最初は「たまたまかな?」と思っていたのですが、これが毎日続くように。
朝の5時って、まだもうちょっと寝ていたい時間帯じゃないですか。急に「ワンワン!」って鳴き声で起こされると、心臓がドキドキして、その日一日が台無しになったような気分になります。
仕事にも影響が出始めて、「これはちょっと困ったな」という状況に。
直接言うか?管理会社に相談するか?
最初は「直接お隣さんに言った方がいいのかな?」とも思いました。でも、これがなかなか難しい。
ペットの問題って、飼い主さんにとっては「可愛い家族」の話なので、下手に言うと感情的になってしまう可能性もあります。
結局、管理会社に相談することにしました。
管理会社への相談と注意喚起文書の依頼
管理会社に電話して、状況を説明しました。「隣室の犬が早朝から吠えて困っている」と。
管理会社の方は慣れた様子で「承知いたしました。注意喚起の文書を掲示いたします」と回答。思っていたよりもスムーズに話が進んで、少し拍子抜けしました。
数日後、エントランスに「ペットの鳴き声について」という注意喚起文書が掲示されました。
予想外の展開:「直接言って欲しかった」という反応
注意喚起文書が掲示されてから1週間ほどで、確かに朝の鳴き声は減りました。「お、効果があったじゃん」と安心していたのですが、ここで予想外の展開が。
隣室の住人の方と偶然エレベーターで一緒になった時、「あの掲示、誰が言ったんでしょうね。直接言ってくれれば良かったのに」とちょっと怒った様子で言われました。
まさか私が依頼したとは思っていない様子で、なんだか複雑な気持ちに。「気づいていなかった」というよりも、「なんで直接言わないんだ」という感じでした。
結果的には改善されたけれど…
その後も朝の鳴き声は以前より明らかに減って、睡眠の質も改善されました。完全になくなったわけではないけれど、許容範囲内には収まった感じです。
何より、「何か行動を起こした」ということで、気分的にスッキリしました。ずっと我慢し続けるストレスから解放されたのは、本当に大きかったです。
注意喚起文書以外の生活音トラブル対処法
注意喚起文書だけが解決策ではありません。他にも効果的な方法があります。
自分でできる防音対策
・耳栓やイヤーマフの活用 睡眠時や集中したい時に使える基本的な対策です。最近の耳栓は性能が良くて、つけていても圧迫感が少ないものが多いです。
・ホワイトノイズアプリの利用 スマホアプリで自然音や環境音を流すことで、気になる生活音をマスキングできます。
・防音カーテンや吸音材の設置 完全に遮音はできませんが、音を和らげる効果があります。
管理会社との効果的な相談方法
管理会社に相談する時のポイントをお伝えします:
・具体的な時間帯と音の種類を記録 「毎朝5時頃から犬が吠える」「平日の夜11時以降にテレビの音が大きい」など、具体的な情報があると管理会社も対応しやすくなります。
・感情的にならずに事実を伝える 「迷惑している」という感情よりも、「こういう音がこの時間帯にある」という事実を中心に話すのが効果的です。
第三者機関の活用
・自治体の相談窓口 市区町村の環境課や生活課で、騒音相談を受け付けている場合があります。
・調停や法的手続き 深刻な場合は、簡易裁判所の調停や法的手続きも選択肢の一つです。でも、ここまで来ると関係修復は難しくなってしまいます。
生活音トラブルを予防するために私たちができること
トラブルが起きてから対処するよりも、予防する方が断然楽です。
日常生活での音への配慮
・時間帯を意識した生活 朝の6時前や夜の10時以降は、特に音に注意を払う。洗濯機や掃除機の使用は避ける。
・床の防音対策 カーペットやマットを敷く、スリッパを履くなど、足音を軽減する工夫をする。
・音量の調整 テレビや音楽の音量は、隣室に聞こえない程度に調整する。
良好な近隣関係の構築
・挨拶やちょっとした会話 普段から顔見知りの関係を築いておくと、何か問題があった時に相談しやすくなります。
・引っ越し時の挨拶 新しく住む時は、隣近所に挨拶をして、「何かあれば直接お声かけください」と伝えておく。
これって当たり前のことかもしれませんが、意外とできていない人が多いんです。
生活音トラブルは、本当に悩ましい問題です。でも、一人で抱え込まずに、適切な方法で解決に向けて行動することが大切。完璧な解決は難しくても、「少しでも改善された」「行動を起こせた」という感覚は、精神的に大きな支えになります。
あなたの生活がより快適になるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
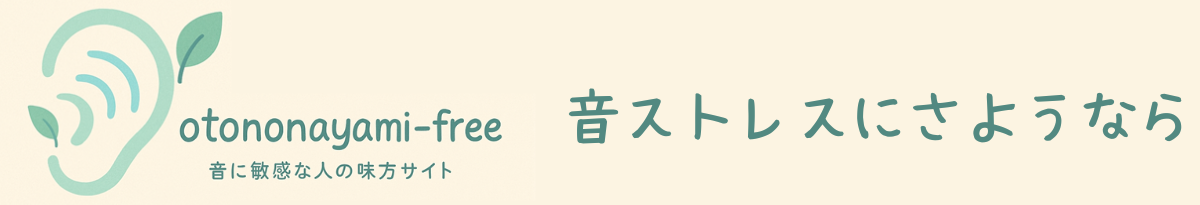
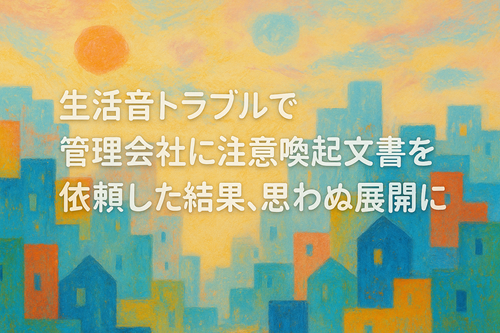
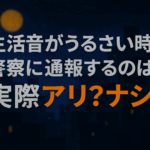
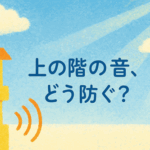
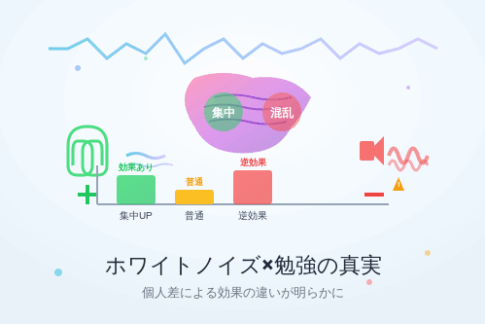
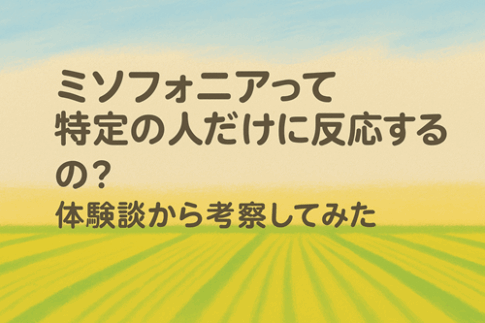
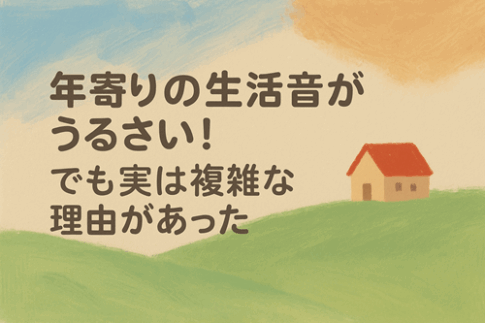
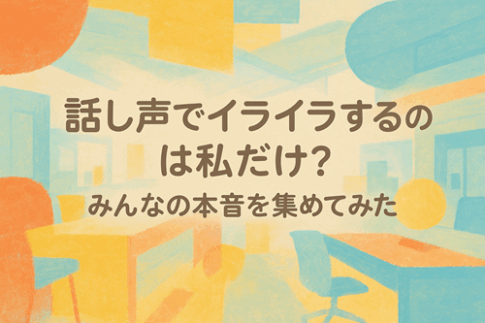
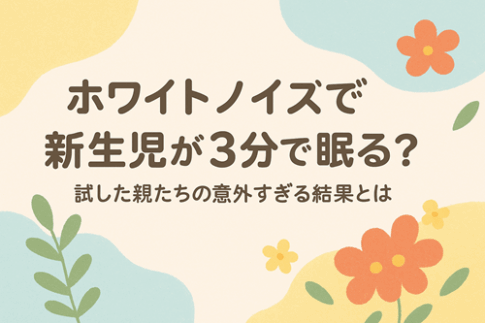
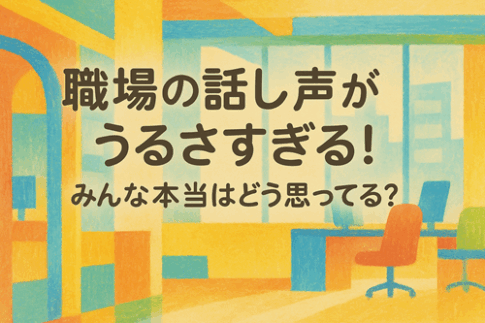
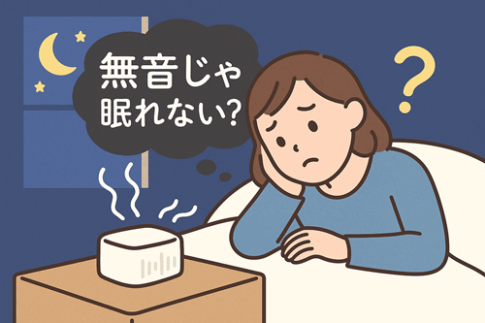
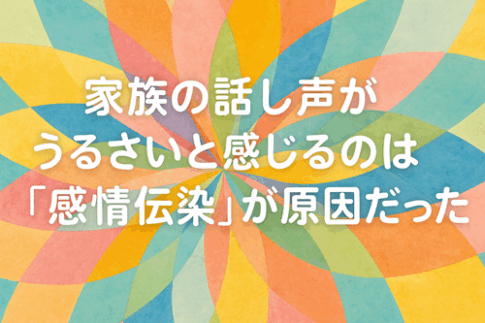
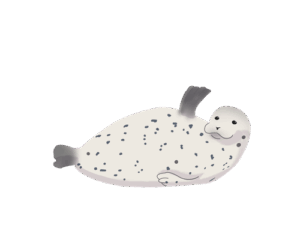
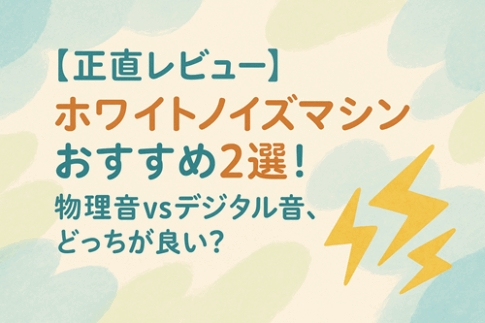


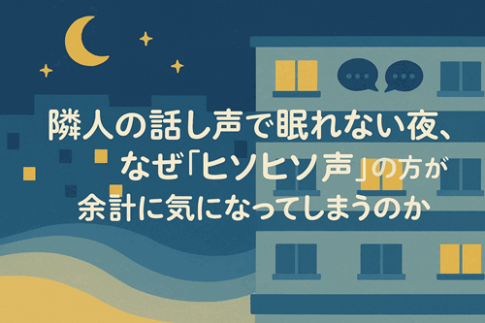
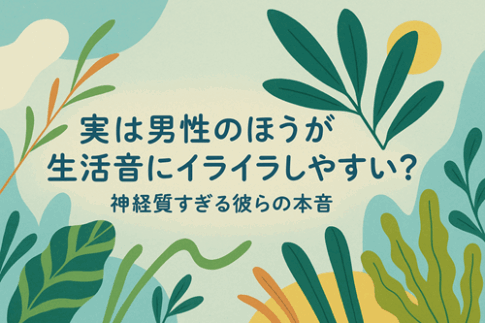
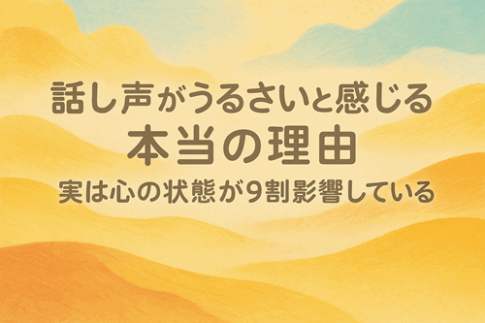
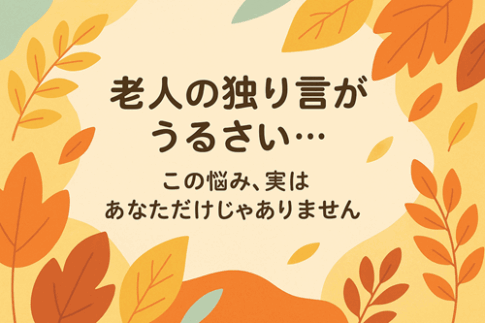
コメントを残す