家族と暮らしていて、ふとした瞬間に「話し声がうるさいな」と感じたことはありませんか?
愛している家族なのに、なぜかイライラしてしまう自分に罪悪感を抱く人は多いもの。でも実は、家族の話し声に敏感になってしまうのは、決して珍しいことではありません。
この記事では、実際に家族の話し声で悩んだ方の体験談を通して、なぜこのような感情が生まれるのか、そしてその気持ちにどう向き合っていけばよいのかを一緒に考えていきます。
なぜ家族の話し声が気になってしまうのか
家族の話し声が気になる理由は、単純に「音量が大きい」だけではありません。
実は、私たちが家族の声に敏感になってしまうのには、いくつかの心理的・環境的な要因が関係しています。まず考えられるのは、家庭環境での音に対する感受性の違いです。
同じ家族でも、音に対する感覚はそれぞれ異なります。テレビの音量ひとつとっても、「ちょうどいい」と感じる人もいれば、「うるさすぎる」と感じる人もいるでしょう。
さらに、世代間のコミュニケーションスタイルの違いも大きな要因となります。年配の方は声が大きくなりがちですし、若い世代は静かな環境を好む傾向があります。
実際の体験談:母親の電話の声が気になって仕方ない
30代の女性、Aさんの体験談をご紹介します。
Aさんは在宅ワークをしながら、70代の母親と同居しています。母親は友人との電話が日課で、毎日2時間程度話しているそうです。
「最初は気にならなかったんです。でも、在宅ワークが始まって家にいる時間が長くなると、だんだん母の電話の声が耳について仕方なくなって」
Aさんによると、母親の電話は決まって午後2時頃から始まります。ちょうど集中して仕事をしたい時間帯と重なってしまうのです。
「声が大きいだけじゃなくて、話の内容も同じことの繰り返しなんですよね。近所の人の話とか、テレビで見た内容とか。聞いているこちらが疲れてしまって」
なぜ繰り返される会話が気になるのか
Aさんの体験談で注目したいのは、話の内容が繰り返されることへのストレスです。
人間の脳は、予測可能なパターンを認識すると、無意識にそれに注意を向けてしまいます。毎日同じような時間に同じような内容の電話が始まると分かっていると、集中していても「そろそろ始まるな」と身構えてしまうのです。
これは決してAさんが神経質だからではありません。音に敏感な人にとって、予測可能な音のストレスは想像以上に大きいものなのです。
私も似たような経験があります。家族が同じテレビ番組を毎日見ていて、CMの音楽まで覚えてしまった時期がありました。愛する家族なのに、なぜかその音が苦痛に感じてしまう自分に驚いたものです。
世代間のコミュニケーションギャップ
もう一つ考えておきたいのが、世代間でのコミュニケーションスタイルの違いです。
年配の方は、電話でのコミュニケーションを大切にする傾向があります。友人や親戚との電話は、社会的なつながりを維持する重要な手段なのです。
一方、若い世代は静かな環境を好み、必要以上に大きな声でのやりとりを避けがちです。この違いが、家庭内での音に対する感覚のズレを生んでしまいます。
兄弟の大声での会話が気になるケース
続いて、別の体験談もご紹介しましょう。
20代の男性、Bさんは大学生の弟と実家で暮らしています。弟は友人とのオンラインゲームに夢中で、夜中まで大声で話し続けることが多いそうです。
「弟のゲーム中の声って、本当に大きいんですよ。しかも興奮すると更に声が大きくなって。隣の部屋で寝ていても目が覚めてしまいます」
Bさんが特に困っているのは、弟の感情の起伏が激しい話し方です。
「ゲームで勝った時の『やったー!』って声とか、負けた時の『うわー!』って声とか。感情がストレートに出るから、聞いているこちらもなんだか疲れてしまって」
感情的な声がもたらすストレス
Bさんの体験談で興味深いのは、感情の起伏が激しい声に対するストレスです。
人間は他人の感情に無意識に共鳴してしまう性質があります。これを「感情伝染」と言いますが、特に家族のような身近な人の感情は、思っている以上に私たちに影響を与えます。
弟さんの興奮した声を聞いていると、Bさん自身も無意識に緊張状態になってしまうのです。それが積み重なると、家にいるのに落ち着かないという状況を作り出してしまいます。
私は個人的に、この話を聞いて「確かに!」と思いました。家族が電話で誰かと口論している時の声って、内容は分からなくても聞いているだけで心がざわざわしてしまいますよね。
夜間の音に対する敏感さ
もう一つのポイントは、夜間の音に対する敏感さです。
夜は本来静かな時間帯なので、昼間は気にならない音でも気になってしまうものです。特に睡眠前後の時間帯は、人間の聴覚がより敏感になっています。
Bさんの場合、弟さんのゲーム時間が夜中にかかることで、より一層声が気になってしまうという悪循環に陥っていました。
家族との音の距離感をどう考えるか
これらの体験談から見えてくるのは、家族との適切な音の距離感の大切さです。
家族だからといって、すべての音を受け入れなければならないわけではありません。お互いが快適に過ごすために、音に対する配慮は必要なのです。
罪悪感を感じる必要はない
まず大切なのは、家族の声が気になることに罪悪感を感じる必要はないということです。
「家族なのに声がうるさいと感じるなんて」と自分を責めてしまう人が多いのですが、音に対する感受性は個人差があって当然です。
愛情と音に対する感覚は別物です。家族を愛していても、生活音や話し声が気になることはあります。それは自然なことなのです。
私も以前は「家族の声が気になるなんて、自分は冷たい人間なのかな」と悩んだことがありました。でも今思えば、それは単純に音に対する感受性が高かっただけなんですよね。
世代の違いを理解する
年配の方が声が大きくなってしまうのには、いくつかの理由があります。
聴力の衰えによって自分の声の大きさが分からなくなったり、昔の生活環境の影響で大きな声で話す習慣がついていたりします。また、電話機器の性能の違いで、必要以上に大きな声で話してしまうこともあります。
一方、若い世代は静かな環境に慣れているため、少しの音でも敏感に反応してしまいがちです。
この世代間のギャップを理解することで、お互いへの理解が深まるのではないでしょうか。
音に敏感な人の特徴を知る
音に敏感な人には、いくつかの共通した特徴があります。
集中している時に音で気が散りやすかったり、複数の音が重なると疲れやすかったり、予測できない音にびっくりしやすかったりします。
これらは生まれ持った感受性の違いであり、決して神経質だったり我慢が足りなかったりするわけではありません。
自分の特性を理解することで、家族の声に対する反応も客観視できるようになります。
まとめ
家族の話し声が気になってしまうのは、あなただけの悩みではありません。
音に対する感受性の違い、世代間のコミュニケーションスタイルの違い、生活環境の変化など、様々な要因が重なって起こる自然な現象なのです。
大切なのは、その気持ちを否定せずに受け入れること。そして、家族との適切な音の距離感を見つけていくことです。
愛する家族との生活の中で、お互いが快適に過ごせる方法を見つけていけたらいいですね。音の問題は解決が難しいこともありますが、まずは「気になって当然」と自分を受け入れることから始めてみてください。
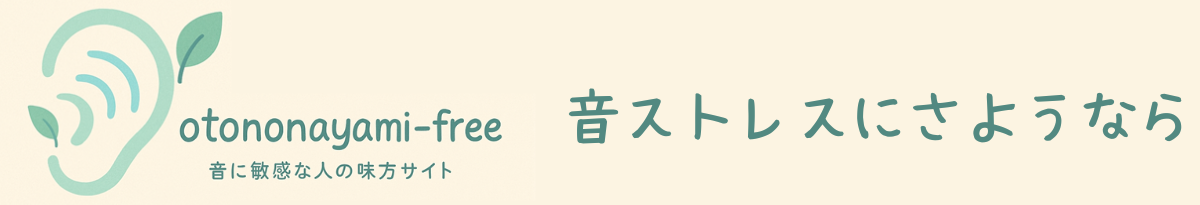

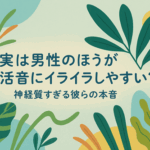
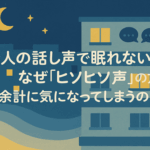
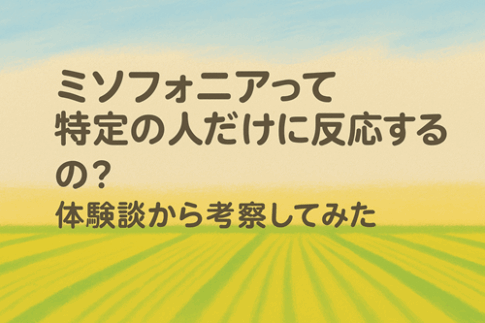
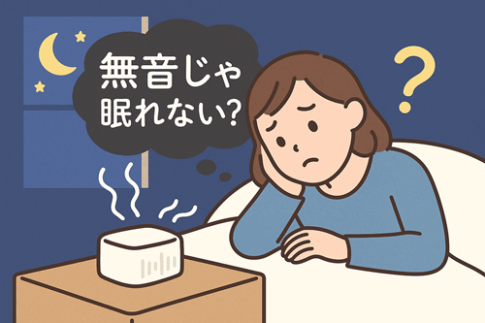
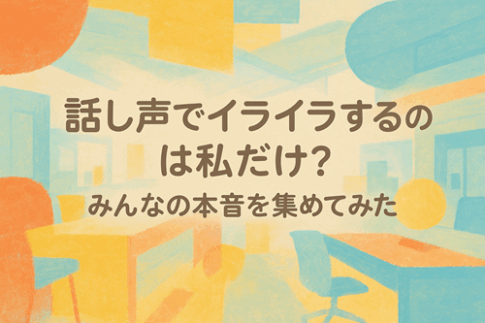
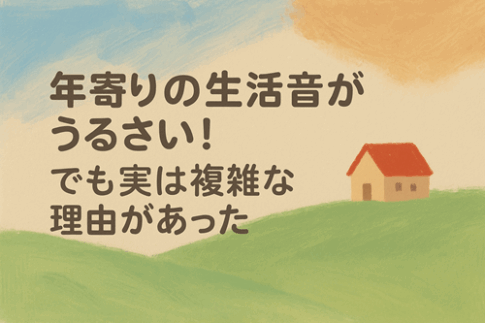
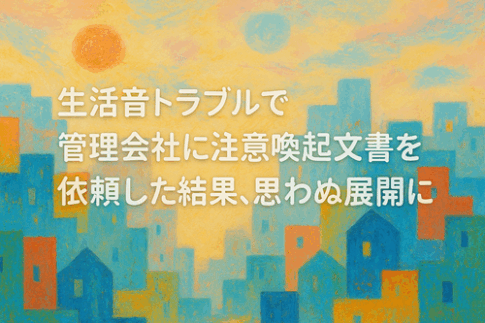
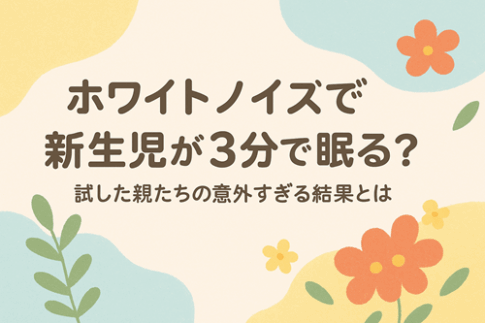
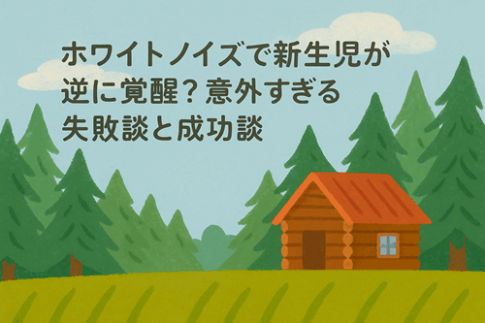

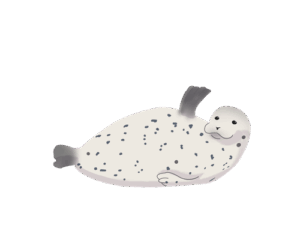
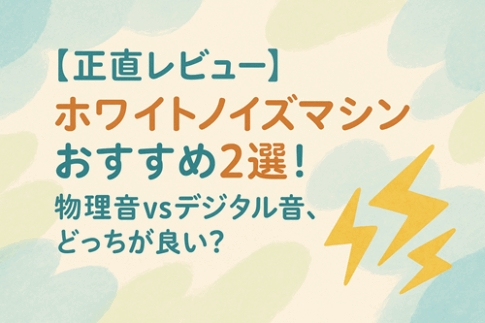

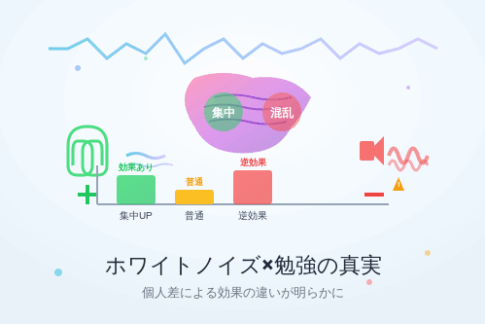

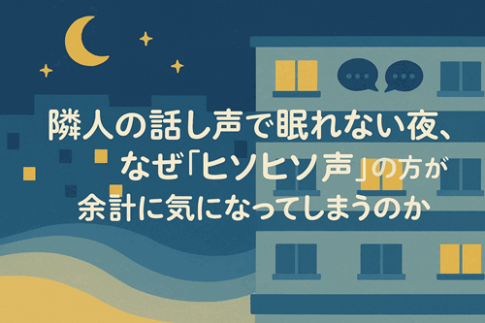
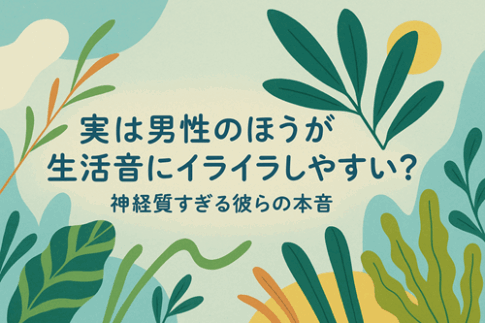
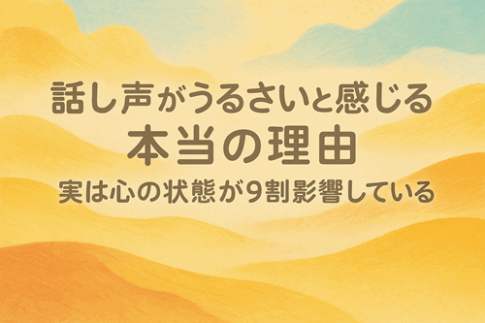
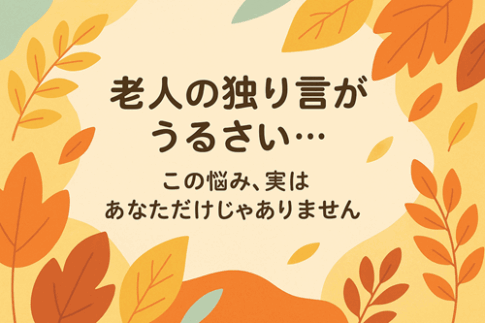
コメントを残す